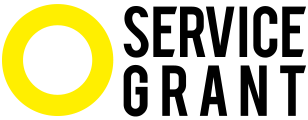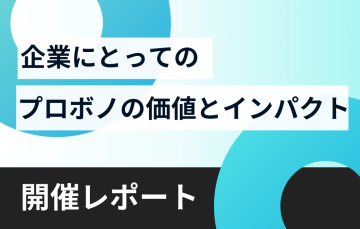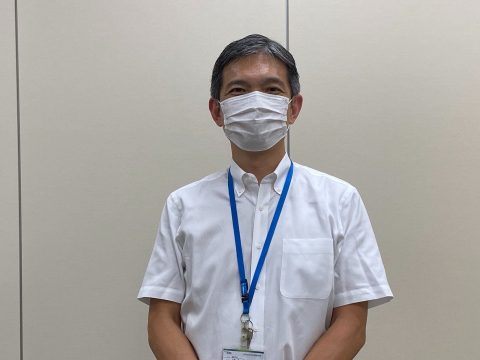
サービスグラントのプロボノの現場から得たノウハウを基に開発した「社会課題解決型人材育成プログラム プロボノリーグ」。今回は2017年よりプログラムに継続して参加頂いているフコクしんらい生命保険株式会社の人事・総務部長小林新様にお話しを伺いました。自律型人材の育成がポイント、とされる同社の背景や今後の施策についてお話し頂きました。
※本記事は2020年のインタビュー内容を再構成しています。企業の取り組み内容等は現在と異なる場合があります。
目次
意識が社内にいきがちな社員の行動変容を促したい
――本日はお時間をいただきありがとうございます。まず、近年の金融業界全体の環境変化について、どのように感じていらっしゃいますか。
ここ最近は特に変化のスピードが速くなっていると実感しています。人口減少や少子高齢化、マイナス金利など、金融業界には逆風が吹いており、競争も一層激化しています。
また、顧客本位の業務運営が強く求められる中、ITを活用したサービスの差別化も進んでいます。外部環境は大きく変わってきていると感じています。
――そうした外部環境の変化を踏まえ、御社の内部環境にはどのような特徴や課題がありますか。
当社は2008年に共栄火災しんらい生命を引き継いだ、比較的社歴の浅い会社です。
スタート当初は業務を円滑に進めるため、生命保険業界経験の豊富な中途社員を多く採用しました。
その後、新卒採用も始め、社員が順調に育っていますが、中途社員と新卒社員の間に世代の空白があるという課題を抱えています。
――世代やバックグラウンドが異なる多様な人材を活かすうえで、どのような現状や課題がありますか。
多様性は新しい発想を生み、相互理解の文化を育む上で重要だと考えています。
しかし、当社では十分に活かしきれていなかった部分があります。例えば中途社員は、自ら望んで入社し、その職務に真摯に取り組む一方で、他人の領域に踏み込まない傾向がありました。
業務運営上は有効でしたが、摩擦を避けない協働姿勢を推進することが必要だったと認識しています。
――多様性を十分に活かしきれなかった背景には、どのような要因があったのでしょうか。
生命保険業界は他業界に比べてビジネスモデルや商品の変化が小さく、社内での調整業務が重視される傾向にありました。そのため、外部環境の変化を積極的に取り込む力が弱まっていたと考えています。
たとえば、商品やサービスの見直しにおいても社内調整に多くの時間を要し、結果として市場変化に迅速に対応できない場面がありました。
ただし、マイナス金利の導入以降は変革の必要性が高まり、当社でも対話やコミュニケーションの推進を通じて変化を促してきました。とはいえ、文化や習慣を変えるには摩擦が避けられず、粘り強い取り組みが不可欠だと考えています。
変化に対応できる自律型人材の育成が急務
――こうした外部・内部の変化を踏まえ、人材育成において 特に重視されている課題は何でしょうか。
最大の課題は、変化に対応できる自律型人材の育成です。社員一人ひとりが自分の見えている課題を全社的に捉え、自ら解決に向けて行動することが求められています。
社員数が多いわけではない当社にとって、全員が主体的に動くことが不可欠です。
――昨今は働き方の変化に伴い、社員一人ひとりに意識の変化が求められていると思います。こうした点について、どのようにお考えですか。
社員が自律的に成長していくためには、単に与えられた役割を果たすだけでなく、自ら課題を見つけ、解決に向けて動く姿勢が欠かせません。働き方が多様化する中で、会社に依存せず、自分の役割を主体的に認識し、行動できることが重要だと考えています。
一方で、すべての社員が同じように意識を切り替えられるわけではありません。新しい環境や働き方に戸惑う社員もいるため、人事としては事前に目的や期待を丁寧に伝え、例えば、研修後のフォローアップを行うことが不可欠です。こうした取り組みを通じて、社員が自らの成長を実感し、組織としても成果につながるよう支援していきたいと考えています。
自律型人材の育成施策

――自律型人材を育成するために、具体的にはどのような施策を進めていらっしゃいますか。
社員の自律性を高めるために、まず社内では全社的な改善提案を促す制度や、チャレンジングな目標を設定できる目標管理制度の改定を進めています。失敗を恐れず挑戦することを奨励し、若手からの抜擢も行うことで、社員の意欲を高めています。
一方で、社内だけでは得られない経験を補うために、サービスグラントの「プロボノリーグ」に継続して参加しています。異業種の仲間と協働し、摩擦を伴いながら課題解決に挑むことで、リーダーシップを発揮する機会となり、社員の行動変容を促す有効な場となっています。
これらを組み合わせることで、社員が自ら考え、行動に移すきっかけをつくりたいと考えています。
――プロボノリーグで提供されるアセスメントレポートについては、どのように活用されていますか。
アセスメントは単なる研修の成果を示す資料ではなく、人材育成を進めるための大切な材料になると考えています。レポートで明らかになった個人の強みや課題を所属部署で理解し、評価指標と照らし合わせて活用することで、実務につながるフィードバックが可能になります。
また、上司と部下の面談や人事部門とのすり合わせの場面でも役立ちます。評価の基準や捉え方の違いを可視化できるため、コミュニケーションを深めるきっかけにもなります。こうした活用を積み重ねることで、組織全体で共通言語を持ちながら育成に取り組めると考えています。
今後の人材育成の方向性
――近年は学びの形も多様化し、オンラインやハイブリッドに加えて、社外に踏み出す越境学習なども注目されています。こうした変化について、どのようにお考えですか。
形式や場が異なっても、社員が自律的に学び、成果につなげることが最も重要だと考えています。実際にオンラインでの研修でも成果を上げた例がありますし、越境学習のように社外の環境で学ぶ経験も、社員の意識変化を促す大きなきっかけになります。大切なのは、社員がその機会をどう活かすかです。
一方で、新しい形式に戸惑う社員もいます。そうした場合には、人事として事前に目的や期待を丁寧に伝え、例えば研修後のフォローアップを行うなど、きめ細かなサポートが不可欠です。形式の違いを越えて社員の成長を支援していくことが、今後の人材育成において重要だと考えています。
まとめ
金融業界における競争激化や少子高齢化といった環境変化の中で、フコクしんらい生命は自律型人材の育成を最重要課題と位置づけています。社員一人ひとりが主体的に課題を捉え、全社的な視点で行動できるよう、社内制度の改定と、プロボノリーグをはじめとする社外での実践機会を組み合わせて取り組んでいます。
また、人事としては社員が新しい挑戦に臨む際に、目的や期待を丁寧に伝え、例えば研修後のフォローアップを行うなど、挑戦を後押しする役割を担っています。
これらの取り組みを通じて、社員の自律性を高めると同時に、組織全体の変革力を持続的に強化していくことを目指しています。