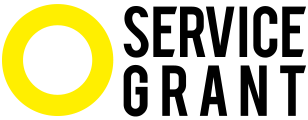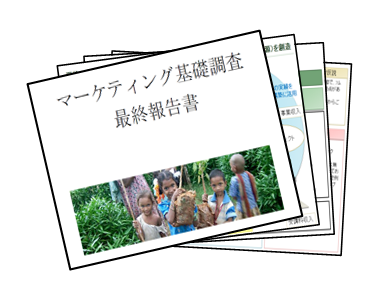プロジェクト紹介
ムラのミライ(旧ソムニード)
ムラのミライ(旧ソムニード)は、20年に渡りインド、ネパール、日本の3か国において”対話”を用いた持続可能な地域づくりを支援している団体です。この海外での活動の中で培われた、自律的な地域づくりに向けた”ファシリテーションのノウハウ”を、日本の地域づくりにも生かしていきたい、国内の地域づくりを担う人材育成に役立てていきたいという思いをもって活動をしています。一方で、対象となる日本国内の研修やファシリテーションに関連する現状把握に課題を抱えており、今回プロボノチームでは、ソムニードの持つ資源(ノウハウ)をどのように国内のニーズに最適化し、どんな対象者に提供できるのか基礎調査をお手伝いします。
NPOのニーズ
ムラのミライ(旧ソムニード)は、インドでのマイクロファイナンスやネパールでの川の浄化といったBOP地域*でのNGO活動を通して対話型ファシリテーションの手法を確立してきました。ムラのミライは、これらのノウハウを活かし、国内でも地域づくりプロジェクトや対話型ファシリテーション講座などの活動を展開しています。
プロボノチームには、自主活動の強化という次ステージへ進むべく、対話型ファシリテーション講座のマーケティング支援が求められていました。
さらに、団体は、プロボノによるマーケット調査の結果をもとに、講座受講料の増収、および、対話型ファシリテーションの普及に伴う寄付金の増収を達成するための、具体的な施策をたてたいと考えていました。
チームの取り組み
『対話型ファシリテーション』講座について、ムラのミライ(当時:ソムニード)の関係者(内部スタッフや大手企業CSR部署担当者、行政研修担当職員など)を対象にヒアリング調査を行いました。また、受講経験者を対象としたeメールアンケートによる追跡調査や、競合分析、市場調査などを実施しました。
これらの調査の結果、対話型ファシリテーション手法は、受講経験者の評価が非常に高いという強みがある一方で、知名度が低く、受講対象者へリーチできていないことが分かりました。また、ソーシャルワーク、ソーシャルビジネスを解決する手段として、事業化に結び付けられるチャンスが大きいことも示唆されました。
そこで、主に、3つの提案を行いました。
1.過疎地域の問題解決と結びつけた解決支援
日本で広がる限界集落、過疎地域の活性化を求める声に対して有用な手法であり、受講と同時に問題解決のコンサルタントができればと期待を込めて提案しました。
2.BOP市場で事業展開したい日本企業の支援
インドで既に実践を通して育った人材の活用提案で、日本企業への展開が期待できると考えました。
3.受講機会をもてなかった個人に対する支援
リーズナブルな価格設定と講座数を増やすことで、機会を増やすことを提案しました。具体的には、講座の質を維持しつつ講座数を増加させるために、講座のマニュアル作成や講師育成、講師の資格レベル設定が必要との提案を行いました。
成果
団体のもつ独特の課題解決の手法を海外だけではなく国内でも展開していくことを、改めてステークホルダーに分かりやすく伝えるため、業界では名の通った『ソムニード』から、『ムラのミライ』へ組織の名前を変更するという大きな変化がありました。
プロボノの提案書をもとに、組織の体制強化や入門セミナーの開設、講師育成など組織強化から改善を始め、次のような成果が上がっていました。
・入門セミナーを新設し、リーズナブルな価格で16回開催した。対話型ファシリテーションとは何か興味を持った方に対する間口が広がった
・基礎講座の開講数を、前年(2013年)10回から2014年13回に増加した
・入門セミナー、基礎講座に関する研修テキストが整備され、英語化も同時に進行。グローバル展開が期待できるようになった
・講師に求められる能力が明確化され、講師の育成が進んだ
プロボノの提案書は、海外の事業所も含めた組織内で回覧し、課題の共有化、意識付けができたと評価をいただきました。
NPOの声
NPO法人 ムラのミライ
専務理事 宮下和佳様
プロボノの皆さまには、講座やフィールドワークの現場に足を運んでのヒアリングに始まり、詳細なデータ分析や競合分析など、とても精力的な調査に基づく提案をしていただき、スタッフ・理事にとって大きな刺激となりました。
講師人材を育成する必要性や国内プロジェクトを広げることの可能性など「薄々気づいてはいたけれど言語化できていなかった課題/日々の業務に追われて手をつけられていなかった課題」も明確にしてくださったので、世代交代しつつある組織の動きの中に、どんどん取り入れることができています。
活動のブラッシュアップ、組織運営の改善は常に取り組むものですが、これらのプロセスをどう進めるかという点でも(分析の仕方、必要な視点・項目・・・など)、プロボノチームの調査内容・提案から多くを学ぶことができました。
ありがとうございました!
進捗状況
- プロジェクトマネジャー:
- 網屋さん
- マーケッター:
- 佐藤さん 田中さん 堤さん 丸谷さん 辻さん
2013.11.24
最終ワークショップ・打ち上げ【MTG】を実施しました。
2013.11.24
調査報告に対するフィードバックと承認を実施しました。
2013.11.24
調査報告 【MTG】を実施しました。
2013.10.05
調査報告事前ミーティング 【MTG】を実施しました。
2013.09.23
ヒアリング以外の調査・リサーチ作業を実施しました。
2013.09.15
外部ヒアリングを実施しました。
2013.09.08
9月9日から約2週間かけて、想定ターゲットの属性についてヒアリング週間を迎えます。自治体研修担当、企業内研修担当、商工会議所など多様な対象者から聞き取りを進めます。
2013.08.31
調査手法についてソムニード宮下さんとミーティング予定
2013.08.19
想定ターゲットのリストアップ、及び、ヒアリング先を出し合い、繋がりのある方に協力要請中。
2013.08.16
内部ヒアリングを実施しました。
2013.08.05
ソムニードさんから想定競合先について情報入手、コンタクトの可否など確認中
2013.08.05
ソムニードさん20周年記念行事に合わせて実施されるイベントなどに各自の都合調整の上、参加予定
2013.08.05
31日にソムニードさんの過去研修参加者属性の洗い出しと今後に想定ターゲットのヒアリングリスト共有、及び、実施段取りを確認しました。
2013.07.17
活動現場体験・見学を実施しました。
掲載情報はプロジェクト実施時点のものです。最新情報は団体のウェブサイト等でご確認ください。
- 日本アウトワード・バウンド協会
- 箕面市国際交流協会
- 社会福祉法人 めぐはうす